加齢に伴う疾患の発症メカニズムを分子・細胞レベルで解明し、その予防や治療法の開発に結びつけることを目指す「ジェロサイエンス」は、近年ライフサイエンス研究の新たな潮流として注目を集めています。細胞の恒常性維持や老化制御に関わる生物学的プロセスとして、オートファジー(自食作用)とセノリティクス(老化細胞除去)は、いずれもジェロサイエンスの中核を担う重要な研究対象です。 オートファジーは、細胞内の不要な構成要素を分解・再利用することで細胞の健全性を保ち、老化や疾患の進行を抑制する役割を果たします。一方、セノリティクスは、加齢に伴い蓄積する老化細胞を選択的に除去することで、組織の機能低下や慢性炎症の抑制に寄与する新たな治療戦略として注目されています。
本セッションでは、オートファジーおよびセノリティクス研究の最前線で活躍する研究者をお招きし、加齢関連疾患の分子基盤、細胞老化の制御機構、ならびに創薬・予防医学への応用に関する最新の知見をご講演いただきます。本企画を通じて、ジェロサイエンスにおける細胞恒常性制御の理解を深め、ライフサイエンス分野における学際的な研究交流と今後の発展に寄与することを目指します。
| 日時: | 2026年2月2日(月)13:00-17:35 |
| 場所: | オンライン配信(Zoomウェビナー使用) |
| 世話人: | 長谷川清(テクノプロ・R&D社)、佐藤太朗(杏林製薬株式会社)、鈴木達也(大鵬薬品工業株式会社)、東田欣也(株式会社モルシス) |
| 連絡先: | お問い合わせは、下記メールまたはTELにお願いいたします。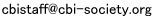 TEL: 03-6435-0458 (情報計算化学生物学会(CBI学会)事務局) |
プログラム
- 13:00 - 13:10 はじめに
- 13:10 - 13:55
「老化の理解からジェロサイエンスの展望へ」
荒井 秀典(国立長寿医療研究センター)
近年、老化の仕組みを生物学的に理解する研究が進み、その成果を人の健康維持へと生かす流れが広がりつつある。こうしたなかで、老化を多様な疾患の共通基盤として捉え、その制御可能性を探る学際的研究領域「ジェロサイエンス」が注目されている。細胞レベルでの老化や慢性炎症、エネルギー代謝の変化など、老化の分子基盤をめぐる研究の進展は、フレイルなど加齢に伴う機能低下の理解にも新たな視点をもたらしている。これらの知見は、老化のメカニズムを「解明する科学」から、健康寿命の延伸に向けて「活かす科学」へと展開するための重要な基盤となる。本講演では、ジェロサイエンスの理念を踏まえ、基礎研究から臨床研究、さらに社会への展開へとつながる老化研究へと広がるジェロサイエンスの今後の展望について考察する。 - 13:55 - 14:40
「神経系におけるオートファジーの生理的意義」
水島 昇(東京大学大学院・医学系研究科・分子生物学分野)
オートファジーは多くの真核生物に備わっている細胞内分解システムである。オートファジーでは、細胞質の一部がオートファゴソームに取り囲まれた後にリソソームへと輸送されて分解される。オートファジーの役割は二つに大別することができる。一つ目は、アミノ酸などの分解産物を調達するための栄養素のリサイクルであり、この機能は飢餓に対する適応や着床までの胚発生などにおいて重要である。二つ目は、細胞内の品質管理や浄化を目的としたもので、変性タンパク質や不良・損傷小器官の除去などを行うものである。この機能は神経細胞変性や腫瘍発生を抑制するものであり、特に長寿命細胞において重要であると考えられる。講演では、特に神経系を中心としたオートファジーの活性評価や、オートファジー不全による細胞機能障害の可逆性などの最近の知見について紹介したい。 - 14:55 - 15:40
「オートファジー・リソソーム機能の制御機構と老化における役割」
中村 修平(奈良県立医科大学 医学部・医学科生化学講座)
超高齢化社会という未曾有の課題を抱える我が国において、多くの疾患の最大のリスクファクターである老化メカニズムの解明し、その知見に基づいた健康寿命延伸法の確立が急務となっています。私たちはこれまでの研究を通して、細胞内分解システムとして知られるオートファジーや、分解とシグナル伝達の司令塔の働きを併せ持つリソソームの機能が老化や寿命制御において中心的な役割を果たすことを見出し、この分子機構の一端を明らかにしてきました。本講演ではこれまで得られた研究成果を中心に、オートファジー・リソソーム機能と老化や加齢に伴う疾患との関連について紹介いたします。
参考
https://researchmap.jp/shuhei - 15:40 - 16:25
「加齢に伴う慢性炎症とこれを標的とした老化病態の改善」
中西 真(東京大学大学院・理学系研究科・癌防御シグナル分野
老化は人類誰もが経験する普遍的は生命現象で、高齢者のQOLに非常に重要である。また老化は人のほとんどの疾患の最も大きな危険因子の1つであるため、老化を理解しこれに介入することは多くの疾患に対する重要な予防医学の確立につながると予想できる。老化は、加齢に伴い蓄積する炎症誘発細胞により分泌される炎症性因子によって引き起こされる全身性の慢性炎症(炎症性老化)を特徴とする。加齢に伴う慢性炎症の本体については未だ不明な点が多いが、近年老化細胞の関与が提唱されている。従って、老化細胞を除去するか、その炎症性性質を抑制できれば慢性炎症が改善し、その結果加齢に伴い低下した臓器機能が改善することが期待されている。しかしながら、これらは未だ生体内での実証が完全ではない。我々は老化細胞除去技術と一細胞トランスクリプトーム解析を組み合わせることで、加齢に伴う慢性炎症の本体と、老化細胞除去効果についての解明を試みたので報告したい。 - 16:40 - 17:25
「Seno-anergyを標的とした抗老化治療の開発」
南野 徹(順天堂大学大学院・医学研究科・循環器内科学教室)
加齢に伴って生活習慣病の罹患率が増加し、その結果、虚血性心疾患や脳卒中の発症の基盤病態となっている。健康寿命を短縮しているこれらの疾患は、多くの高齢者において共通に認められることから、老化の形質の一部として捉えることができる。すなわち、これらの疾患の究極的な治療のターゲットは、寿命を調節する仕組みそのものかもしれない。このような現状で、老化・寿命のメカニズムの解明に関する研究は、最近20年間で飛躍的な進歩を遂げている。老化のメカニズムについては諸説あるが、そのひとつが「細胞老化仮説」である。加齢や過食などのメタボリックストレスによって、様々な組織に老化細胞が蓄積し、それらが分泌する炎症分子による組織障害や組織再生能力の低下によって、臓器老化・個体老化が進むというものである。実際我々はこれまでに、血管や心臓、内臓脂肪組織に老化細胞が蓄積することで、それぞれ動脈硬化や心不全、糖尿病の発症・進展に関与することを明らかにしてきた。さらに最近、老化細胞除去(Senolysis)によって、病的老化形質が改善することが示されている。そこで今回は、老化細胞を標的とした抗老化治療(Seno-antigen, SASP, Seno-anergy-related molecule)の可能性について議論してみたいと思う。 - 17:25 - 17:35 おわりに
<14:40 - 14:55 休憩>
<16:25 - 16:40 休憩>